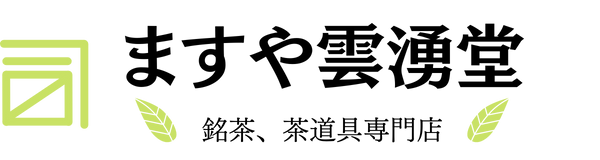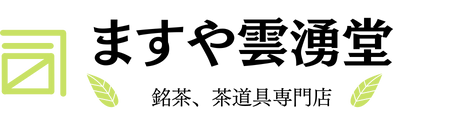★商品状態について★
ユーズド商品です。
金箔の一部に剥がれがありますのでご承知ください。
各部画像にてご確認ください。
名工川本光春作の木魚香合の作品です。
立体的でとても美しい造形の香合で、祥桑軒の名の通り、とても上質な桑材が使用されています。
内側は金張です。
桑材のスペシャリストによる美しい作品をどうぞ。
取り合わせは音や寺院や追善などにちなんでも使えそうです。
共箱付きでの販売になります。
★寸法★
高さ 3.7cm
縦横 7cm×6cm
◆二代 川本 光春(かわもと こうしゅん)
昭和9年、京都生まれ。指物師初代川本光春の長男。
59年2代光春を襲名。
初代が淡々斎より祥桑軒(しょうそうけん)の軒号を頂き、桑材を主体に古来の伝統を守りながら、現代の茶道に見合ったデザインをとり入れ、桑の美しさをいかせる形の表現につとめる。
■木魚の歴史は大変古く、室町時代に始まるといわれています。
山梨県の「雲光寺」にある広葉樹で作られた木魚が、日本の木魚の元祖であるというのが一説です。
この木魚には「応永4年」と刻銘されていたため、木魚は室町時代からあったことが推測できます。
また室町時代には禅宗寺院の中で、大衆を集めるため木製の鳴り物が使われていたことも、木魚の由来の一つとされています。
●木魚を叩く習慣は江戸時代から
室町時代から歴史のある木魚ですが、仏教法具として叩く習慣は江戸時代からといわれています。
江戸時代に中国から渡来した高僧の隠元(いんげんりゅうき)が、明朝の禅を行なったときに木魚を叩いて使ったことで、本格的に仏事に木魚が使われ始めたといわれています。
●楽器としても使われてきた
木魚は仏具としてだけでなく、昔から打楽器としても使われてきました。
仏教法具である木魚を楽器にすると、罰当たりだと思う人も少なくありません。
しかし木魚は中国で、古くから楽器としても使用されています。
歌舞伎の下座音楽などでも使用されており、実は昔から打楽器として使われていたのです。
現代では「テンプルブロック」と形を変え、クラシック音楽などでも親しまれています。