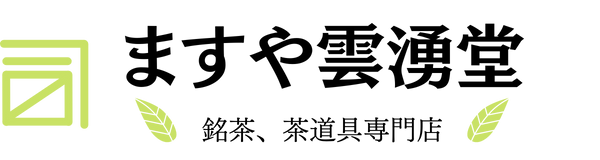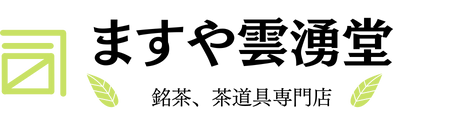★商品状態について★
ユーズド商品です。
経年と使用感がありますので、お安くなっております。
各部画像にてご確認ください。
釜内部は湯鳴りがなく、多少錆が見えますが、湯を沸かしましたが水漏れもなく美味しいお湯が沸きました。
まだまだ使っていただけます。
裏面には色変わりがあり、共蓋はついておりますが唐銅蓋はついておりません。
端立はしっかりとしており、釜に添ったもので十分お使いになられます。
名工釜師大国藤兵衛作の裏甲釜(うらごうかま)の作品です。
少し荒っぽい釜肌が経年と相まって良い味になっています。
赤っぽい色つけがなされたお釜です。
経年があるためお安くなっておりますが、まだ使っていただけますのでぜひご検討くださいませ。
共箱付きでの販売です。
釜鐶は付属しておりません。
★寸法★
全高 19.5cm
全径 33.3cm
胴径 26.5cm
◎表千家では、3月に透木釜、4月に釣釜を使われますが、裏千家では、3月に釣釜、4月に透木釜を使われます。
どちらも五徳の蓋置を良く使われます。
●大國藤兵衛
初代 名を大吉、のちに柏斎の号を賜る。幕末、弟 籐兵衛と共に徳川将軍家の大砲を鋳造す。
二代 名を籐兵衛。大正四年、日本美術協会に鬼霰手取釜を出品。最高賞頂く。
三代 籐兵衛 柏斎、籐兵衛没後其の技術を受け継ぎ茶道隆盛と共に茶人の認めるところと成り、京の大西家に対し浪速の籐兵衛といわれる。
四代 藤兵衛 父(三代藤兵衛)がこよなく愛した芦屋釜、天明釜を研究し独自の釜肌を研究会得。
五代 藤兵衛 早々隠居
六代 藤兵衛(当代) 代々続いた昔ながらの技法による釜肌の美しさを生かし、日々努力をおしまず一歩一歩向上のの道に励んでいる。
◆裏甲釜
宗旦好。いり鍋を逆さまにして底と口を改造した茶釜。いり鍋を逆さにした形姿。
裏ゴウ釜のゴウは、透木釜の羽に鐶付がなく、両方に取手のついているのをごうの釜、又ごう取手の釜と古くは呼んでいる。
ごうは寄せかけるという意味で、取手を釜に寄せかけておくからの名と言われている。
この取手を切掛釜の腰に裏側から仕付けて透木釜に直したところから「うらごう釜」の名が生まれてきたと思われる。
胴と底の部分に段があり、裏の取手は鉄の舌のような形をした物が二枚あり、これを両脇の裏へ差し込んで透木釜に使用し、取れば普通の五徳据えの釜になる。