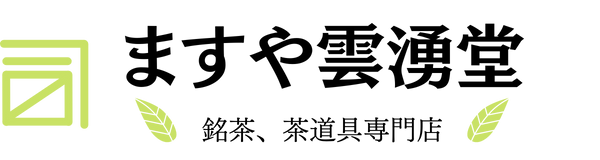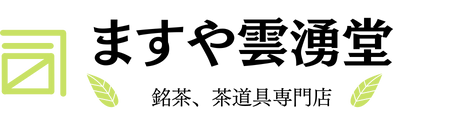★商品状態について★
無疵で綺麗な状態の商品です。
購入されたままの状態なので、拡大画像にてご確認ください。
人気の茶飯釜が入荷しました!
参考定価票は昔のものです。
新品を購入希望の方、良品お探しの方は是非どうぞ!
共箱、替え蓋、釜鐶、経歴、共布、布袋付きでの販売です。
★寸法★
高さ(摘み含む) 20cm
径. 23cm
◆茶飯釜(ちゃめしがま)
茶の湯釜の形状のひとつで、口造りが大きく広い皆口で、羽がつき、丸底の飯炊釜の形の釜です。
茶飯釜は、茶飯茶事に使われ、大きな一文字蓋と、中央に穴をあけた蛇の目蓋と中央に置く小さい蓋が添っていて、飯を炊く際には大きい一文字蓋を使い、茶を点てる時は蛇の目蓋と小さい蓋を使います。
茶飯釜は、宗旦が弟子の銭屋宗徳(ぜにやそうとく)に贈ったものが本歌とされ、宗徳釜ともいわれ、宗旦と宗徳の参禅の師である清巌宗渭(せいがんそうい)の「餓来飯」(うえきたりてめし)「渇来茶」(かわききたりてちゃ)の語を鋳出したもので、宗徳は生涯この釜一つを自在にかけて、飯を炊き、湯を沸し茶を点て、このため一釜宗徳とよばれ、自在庵一釜斎と号したといいます。
★作家★
●菊地政光(きくちまさみつ)
1,937年1月19日生まれ。山形県出身。
奥州山形鋳物の伝統を受け継ぐ。
日本伝統工芸展に意欲的に出品。1,973年の初入選以来、10回の入選を果たす。
1,978年、第五回伝統工芸武蔵野店では日本工芸界東京支部賞を受賞。
同展には10回の入選を重ねるほか、日本伝統工芸新作展では一四回、伝統工芸日本金工展では一二回の入選歴を持つ。
その作風には、つねに新しい感覚が採り入れられている。
1,982年、日本伝統工芸士に認定される。 日本工芸会正会員。