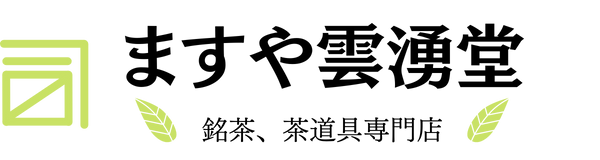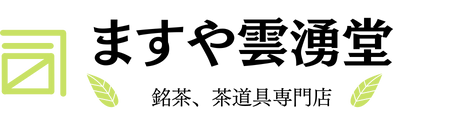★商品状態について★
ユーズド商品です。
無疵で少し使用感がありますが、まだまだ使っていただける商品です。
拡大画像にてお確かめください。
内側に少し錆がありますが、IHで沸かして確認しましたが美味しいお湯が沸きますので、安心してご使用ください。
釜肌もほとんど綺麗ですが、少しだけ変色部分がありますので、拡大画像にてご確認ください。
お湯に色変わりはありませんでした。
※とても人気のある裏千家八世又玄斎一燈好の透木釜です。
口四方で、又隠の鋳込みがあり、鉄の蓋が添えられています。
こちらは中古の商品が入ってくることが珍しいお品ですので、お探しの方はぜひどうぞ!
この商品は共箱、透木、釜鐶付きでの販売です。
◇透木釜の名称の由縁である透木は、敷木(しきぎ)から転訛した言葉と言われます。
釜の羽を支え、炭火がおきやすいよう通風をよくする役目を持っています。
炉縁ぎりぎりの大きな羽の釜は炭手前で釜を上げたりかけたりする場合、炉縁を傷つけないよう、羽根が小さい釜は左右が均一に透木に乗るよう、十分気をつける必要があります。
表千家では、3月に透木釜、4月に釣釜を使われますが、裏千家では、3月に釣釜、4月に透木釜を使われます。
どちらも五徳の蓋置を良く使われます。
★寸法★
高さ(摘み含む) 約19.5cm
径 約33cm
透木 長さ12cm 幅 2cm 厚み1.2cm
★作家★
菊地政光(きくちまさみつ)
1,937年1月19日生まれ。山形県出身。
奥州山形鋳物の伝統を受け継ぐ。
日本伝統工芸展に意欲的に出品。1,973年の初入選以来、10回の入選を果たす。
1,978年、第五回伝統工芸武蔵野店では日本工芸界東京支部賞を受賞。
同展には10回の入選を重ねるほか、日本伝統工芸新作展では一四回、伝統工芸日本金工展では一二回の入選歴を持つ。
その作風には、つねに新しい感覚が採り入れられている。
1,982年、日本伝統工芸士に認定される。 日本工芸会正会員。