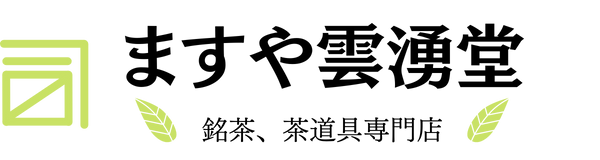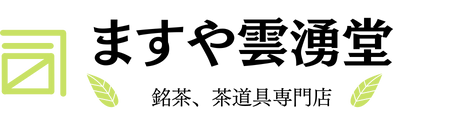★商品状態について★
中古商品ではありますが、使用感はほとんどない、とても綺麗な状態の商品です。
当店で疵のチェックを入念に行っておりますが、無疵ですので安心してお買い求めください。
萩焼ですのでもしかしたら使い始めは軽度の水漏れがあるかも知れませんが、萩の七化けとともにお楽しみください。
十一代三輪休雪 「彫銘」作品が入荷いたしました。
最上位作のうちの一つです。
作品は片身かわりで、一方は休雪の代表的な作風である白萩です。
「休雪白」と呼ばれる純白に近い萩焼は多くの方を魅了し、代表的な作風となっています。
もう一方が萩焼らしい土に白の釉薬がかかっております。
梅花皮のような景色が全体に現れており、存在感に拍車をかけております。
釉薬と土のコントラストは春の雪解けのようで、まさに休雪といった出来でございます。
惚れ惚れするような良いお茶碗で、当店にも飾っていますが存在感が尋常ではありません。
大きさも堂々として立派です。
ちょうど正面に当たる部分に白萩の土見せがあり、洒落ています。
※表千家十四代御家元 而妙斎宗匠より御書付をいただいております。
銘は「井葦水」で、「せいいすい」と読みます。
井をせいと読み、葦をいと読みます。
とても綺麗な水を表した言葉で、飲むと長寿、健康になるという謂れもあります。
凛とした姿から清らかな水を連想し、健康、長寿を願って付けられた銘なのかなと、思いを馳せます。
もともとの休雪のお箱の蓋とは別に、宗匠の御書付のいただいた蓋を造っていただいております。
つまり共箱の蓋が二枚あるということです。
どちらも盛蓋の薬籠蓋で、きっちりと箱に合うものです。
それとは別に塗の外箱が添えられております。
このお箱も盛蓋の四方桟蓋です。
近頃では人間国宝の作品も身近な物になりつつあります。
後に休雪の名を譲り、寿雪に改号しますが、この頃は十一代休雪として作陶していたときの作品です。
これほどのお品は出会うことがほとんどありません。
気に入った方はぜひどうぞ!
★寸法★
高さ 9.2cm
径 14.2cm
●三輪休雪(十一代) みわ-きゅうせつ
1910-明治43年2月4日生まれ。山口県出身。本名は節夫(さだお)
兄三輪休和(10代休雪)川喜田半泥子(はんでいし)に師事。
昭和32年日本伝統工芸展に初入選。
昭和42年十一代休雪襲名、三輪窯を継承。
昭和58年重要無形文化財「人間国宝」に認定。
平成15年長男竜作に休雪の名をゆずり、寿雪と改号。
★配送に関して★
高級品ですので、必ず無事に届くよう、細心の注意を払って梱包いたします。
当店で別途保険料を支払って配送しますが、その保険料や手数料等は一切請求しませんので安心してお買い求めください。(北海道、沖縄、離島などへの配送、支払い方法による手数料などは他の当店通常商品と同じように発生しますのでご了承くださいませ。)